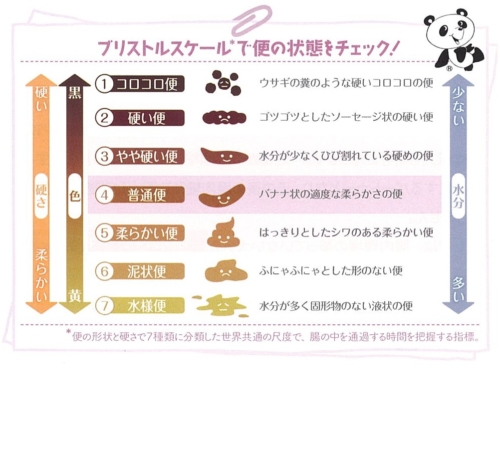新型コロナウイルス感染症が起こり始めて、2年半も経ってしまいました。現在もまだ収束には至っておらず、このままコロナウイルスと共生していかなくてはいけないのかもしれません。
ウイルスや細菌などについてはさまざまの研究がなされていますが、今回は細菌について述べたいと思います。細菌は地球上の生物の1/2~1/3を占めているとされています。それは我々人間の体も例外ではなく、外部環境と接する皮膚や粘膜面には、膨大な数の共生細菌群(常在細菌叢)が定着しています。(下の表に体の各部位のおおよその菌の桁数をまとめてあります)特に大腸は細菌の生育に最適な環境であり、地球上のあらゆる環境中でもとびぬけた高密度で細菌群が棲息(せいそく)するとされています。その数は40兆個以上とされ、宿主の人間の細胞数よりも多いのです。また、細菌の数だけでなく、その多様性が人の健康にどのように影響しているのか。これまで多くの研究報告では、様々な菌の種類がバランスよく存在することがメリットをもたらし、病気になるときにはその多様性が低下することが報告されています。例えば、特定の菌が腸内で増殖すると相対的に菌数が減少します。これは病気の人に多く見られる状態です。一方でさまざまな種類の菌がいると多くのことに対応できる状況になるのです。
表 体の各部位の菌数
| 部位 |
細菌のおおよその桁数 |
| 結腸(大腸) |
10の14乗 |
| 歯垢 |
10の12乗 |
| 回腸(下部小腸) |
10の11乗 |
| 唾液 |
10の11乗 |
| 皮膚 |
10の11乗 |
| 胃 |
10の7乗 |
また、環境が改善して感染症が減少してもアレルギー疾患や自己免疫疾患増加しているのは、環境中の細菌が減少したことに起因されるという「衛生仮説」が存在し、そのことを科学的に証明する研究が盛んにおこなわれています。この衛生的な環境が現代病を増加させるとも言われる中、我々はこのコロナ禍において手指の消毒やうがいを行い、更には自分達の生活圏を消毒し身の周りの菌を減らしてきました。このことが後になって私たちの体にどんな影響を及ぼすのかは、計り知れないところです。(コロナ禍の影響は、この細菌のことのみではないのですが…)
人の疾患と腸内細菌叢
基本的に健康であれば腸内細菌叢の頑健性は保たれています。一方で腸内細菌叢のバランスが乱れる要因はさまざまなものが知られています。
・偏った食事
長期的な食習慣がその人の腸内細菌叢のタイプを決定しています。また、短期的にも極端に食事が変化すると、腸内細菌叢は変化することがわかっています。
・ストレス
脳と腸は迷走神経でつながっており、脳がストレスを感知すると腸の蠕動運動が影響を受け、その結果腸内環境が変動し、細菌叢が変化すると言われています。また、ストレスによって副腎資質ホルモン(ステロイドホルモン)が消化管に分泌されて細菌叢を変化させているとも言われています。
・その他
その他には、生活環境(田舎で暮らしているか都会で暮らしているか、これは細菌が多い環境か少ない環境がということです。食事と一緒に細菌が入ってきます。)、抗生物質などの薬の摂取、加齢などが知られています。
腸内細菌叢がもたらす疾患
腸管は粘膜免疫の中心です。腸内細菌叢がその人の粘膜免疫に影響していることは多くの研究で分かってきています。その中で衝撃的であった研究は、腸内細菌叢が肥満にも関係する報告でした。それは太った人・痩せた人由来の細菌叢を無菌マウスにそれぞれ移植し、その後同じ食餌条件下で太った人由来の細菌叢を移植したマウスの方が太ることを示したものでした。また、この研究では太る原因は、太ったマウスは腸内細菌叢による食餌成分の代謝により栄養素がより多く供給されることで太ってしまうことが報告されています。
この研究をきっかけに、腸内細菌叢と消化管疾患や代謝疾患、がん、免疫疾患、精神疾患、循環器疾患など多くの病気との関連が多数報告されています。
腸内細菌叢をどのように制御するのか
健康を維持していく為に、いかにして腸内細菌叢をコントロールすればいいのか。基礎研究においての代表的な制御方法はプロバイオティクス(乳酸菌やビフィズス菌)やプレバイオティクス(オリゴ糖や食物繊維)の摂取と便移植法です。(便移植法はまだ通常の治療法にはなっていません。)
数年前から多くの食品メーカーからいろいろなヨーグルトが発売され、ブームとなりましたが、これも腸内細菌叢が、病気に大きく関係していると分かった結果です。私たち日本人が腸内細菌叢を維持していくには、日本の伝統的な発酵食品を摂ることが一番いいのではないか、と私は考えています。長い時間をかけて伝統的な酵母菌や麹菌が、我々の腸内細菌叢を維持し健康を支えてきたのですから。だからヨーグルトではないのかなぁと…、と思ったりもします。
日本人には日本人特有な腸内細菌叢のタイプがあるのです。
多くの日本人の腸内細菌を調べた研究では、いくつかのタイプに分類できました。
その中で病気になりやすいタイプの腸内細菌叢は、高たんぱく・高脂肪食(西洋食)を好んで食べている習慣がある人たちです。一般的に良い細菌叢の食事は、低たんぱく・低脂肪・高食物繊維の食生活でした。
人間の3大栄養素であるタンパク質・脂肪・炭水化物は食生活にはある程度必要なのですが、偏ってしまうのはよくないことです。特に日本人は伝統的に食物繊維が多い食生活をしてきました。また、日本食は油の量が少ないヘルシーな食事です。いつもの食生活を見直し、その中に日本の伝統的な発酵食品をプラスする工夫をされたら宜しいのではないでしょうか。
私が子供の頃には、母親が自宅で白菜漬けやぬか漬けを作っていました。この夏、ひと手間かけてトライしてみてはいかがですか。添加物や菌を殺して出荷しているような工場で作られた漬物とは全然違うはずですよ。
主な発酵食品
豆類 : 納豆 醤油 味噌 豆板醤 豆腐ようなど
魚介類 : 鰹節 塩辛 くさや 魚醤 アンチョビ 酒盗など
肉類 : 生ハム サラミなど
乳製品 : チーズ ヨーグルト サワークリームなど
野菜・果物: ぬか漬け キムチ ピクルス ザーサイ メンマ かんずりなど
穀物 : 甘酒 米酢 黒酢 みりんなど
日本で手に入る発酵食品です。この中から自分に合った発酵食品をいくつかとっていただけるといいと思います。